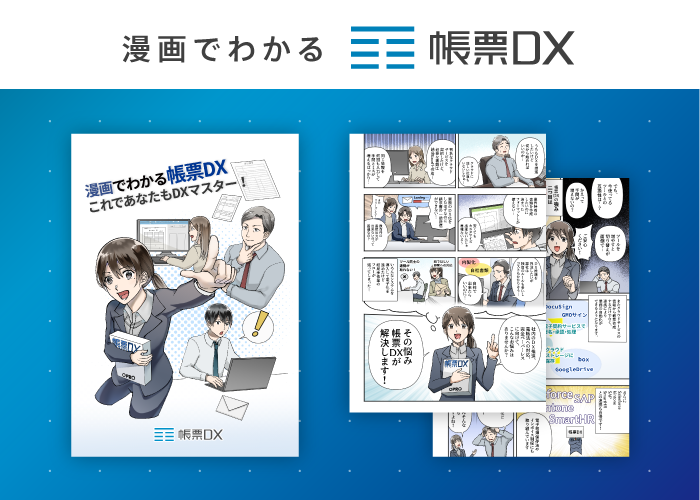導入事例
株式会社TBM

フォーム
帳票DXのサービス資料を
ダウンロードいただけます。
目指すは"100年後も持続可能なイノベーションの創出"
世界から求められる企業が取り組むDXに帳票DXが選出

管理本部 情報システムチーム マネージャー 兼 DX推進委員会 委員長 梁田 将史氏
資源循環事業本部 Maar事業部 小林 綾氏
プラスチック・紙の代替素材となる環境配慮型素材『LIMEX(ライメックス)』の開発・製造・販売や資源循環事業を通じて、プラスチックのリデュース・リサイクルを推進する株式会社TBM。「進みたい未来へ、橋を架ける」をミッションに掲げ、常識にとらわれない非常識な挑戦を誓いとして具体化した「TBM Pledge 2030」を基軸に事業を展開している。昨年のダボス会議では代表の山﨑氏がセッションに参加し、CO2を資源として活用するカーボンリサイクル技術を用いた新素材について発表するなど、海外からも高く評価されるユニコーンスタートアップ企業だ。スタートアップならではのスピード感ある事業展開で急成長する同社は、その事業を支えるひとつのツールとしてオプロの『帳票DX』を導入した。今回は、『帳票DX』どのように活用いただいているかを、全社的なDX推進に関わる梁田氏と小林氏に伺った。
- 【課題】「非常識な挑戦」を続ける企業が決めた 次のステージに向かうためのDX
- 【選定】既存製品を持ちながら生まれた『帳票DX』への期待があった
- 【運用・評価】煩雑な処理を解消し対応工数を1/2に削減 属人化しないシステムのベースができた
- 【今後】次のステージは海外 ますます拡がる事業を支える機能強化にも期待
【課題】「非常識に挑戦」を続ける企業が決めた、次のステージに向かうためのDX
「"100年後も残る技術や事業を作って時代の架け橋になる"という意味を込め、『Times Bridge Management』の頭文字をとって社名としています。サステナビリティ事業をメインとしており、『100年後も持続可能な資源循環イノベーションの構築』を目指す姿(Vision)と、その行動の基盤となる価値観(Value)を5つ掲げています。私を含めて、このValueに共感してジョインする人が多いですね。さらに、CEOの山﨑のメッセージ『サステナビリティ革命の実現』の中で述べられている "進みたい未来を自分たちで作り出す"を体現すべく各々が活動している会社です。私が全社横断のプロジェクト『DX推進委員会』を立ち上げたのもそうした活動のひとつです。」(梁田氏)

冒頭の梁田氏の会社説明を聞くだけで、同じ志を持って未来に突き進む企業集団であることが伝わってくる。同社が帳票DXの導入に至ったDX推進委員会の起案者でもある梁田氏に、どのような形で委員会を運営しているのかを伺った。
「私はコーポレート管理本部コーポレート部の情報システムチームでマネージャーを務めています。チームの役割としては、いわゆる社内インフラや各種ツールの運用保守がメインです。しかし、事業拡大してメンバーが増えていく一方でサイロ化しつつありました。まずは独立しているシステムを全社最適に戻すこと、さらに活用進むAI技術などのテクノロジーの活用を推進していくこと。そして旗を振って推進していくメンバー、つまりはDX人材の育成が必要だと思い、さまざまな部門からメンバーを集める形で委員会を発足しました。現在事業部ごとのDXについて企画検討していて、その責任者という形で私が統括しています。」(梁田氏)
営業やマーケティングのみならず工場所属の人材も参加しながら全社のDX推進に取り組んでいるという。「こうした取り組みはデジタルリテラシーがある人材だけで取り組んでも進まない。」と梁田氏は話す。
「現場の業務やその流れが分かるようなビジネスリテラシーがあり、かつ推進力があるメンバーが必要です。私のミッションはそういうDX人材を育成することかなと思って取り組んでいます。」(梁田氏)
次に、DX推進委員会のメンバーとしても参画する小林氏にも話を伺った。
「私は資源循環事業本部のMaar事業部というところに所属しています。Maar事業部の「Maar(マール)」とは当社の資源プラットフォーム事業のブランド名で、循環の「環」("わ"="まる")や、循環="まわる"という意味で含んでいます。資源循環事業本部では、資源循環プロデュース事業、リサイクルプラントの運営、資源循環プラットフォーム事業、再生材や再生材製品の開発・製造、の4つのビジネスを展開しています。私のメイン業務は、資源循環プロデュース事業を中心としたMaar事業部のバックオフィス業務などの営業支援です。資源循環プロデュース事業の主軸である再生材のマッチングとは、再生可能プラスチックの売り手と買い手をマッチングする事業です。」(小林氏)

先陣を切る欧州をはじめ、世界が注視するビジネスと環境保全の両立。資源を捨てずに再利用することで環境への負荷を低減させるサーキュラーエコノミーの推進が加速する今、同事業は環境配慮型素材の普及に並ぶもう一つの柱として同社が世界から注目される大きな所以だろう。
TBM社は国内に2つの工場を有しLIMEXの製造や再生プラスチックの生成などを手がけているが、どちらの拠点もかなり大規模なものだ。スタートアップ企業にこうした設備投資などはかなり大きな負担となるだろうが、それら事業に大きな期待と共感を抱き投資する企業も多いという。「そうしたパートナ―に支えられて我々は志道を進むことができます。」と梁田氏は話す。
そんな同社がSalesforceを導入したのは昨年のことだ。
「先にLIMEX事業本部が導入し、半年後くらいにMaar事業部にも導入しました。もともと当社の業務分掌として、一人の営業がマーケティングからインサイドセールス・フィールドセールス、カスタマーサクセスまで、一連のプロセスを一人で担当するという体制でした。この体制だと個人差が顕著に出る。結果、トップセールスが屋台骨を支えるような形になっていました。今後事業を拡大していくには、プロセスごとに専業化する体制に変えることが必要だなと。その時に、各プロセスをうまくつないでいくための仕組みが必要だということになり、Salesforceの導入に至りました。もう一つの目的としては、営業の型化です。トップセールスのノウハウはもちろん、個々が持つうまくいったケースなども共有し、システム的に落とし込むことで、全体を底上げすることができる。この二つの目的に対応しうるツールとしてSalesforceを導入しました。」(梁田氏)
「それまでは営業の案件管理から受発注・納品、支払管理をすべてスプレッドシートで実施。あらゆる目的のスプレッドシートも乱立していた上、請求書などの帳票出力のために別ツールにデータのダブル入力が必要だったり、承認の旨が記載されたメールの画面キャプチャを帳票と一緒に保管したりと、かなりの作業工数がかかっていました。Salesforceの導入でデータの一貫した管理体制が作れましたね。さらにそのデータをアウトプットするツールとして帳票DXの導入を決めました。」(小林氏)
【選定】既存製品を持ちながら生まれた『帳票DX』への期待があった
「私が前職でSalesforceに少し触っていた時にやはり帳票出力の話になり、その時にオプロの『オプロアーツ』の存在を認識しました。今回はSalesforceの営業の方からオプロさんをご紹介いただいたことがきっかけになっていますね。ちょうど帳票DXが出た頃だったのですが、もともとオプロアーツというサービスを提供している中で後発製品を出されたことにも『おっ』と思ったというか。既存製品のバージョンアップが多い中、攻めているなと。オプロアーツでの知見とノウハウが詰まった製品だろうという期待もありました。」(梁田氏)
思いがけず嬉しいお言葉をいただいたが、複数のツールをご存じである梁田氏は選定基準もお持ちだっただろう。どのあたりを重視されていたのかをさらに伺った。
「まずはコスト面です。こうしたツールは従量課金制であることが多いですが、帳票DXはライセンス無制限で使えるというのが良かった。今後社員もどんどん増えるだろうという中では大きな要素です。次に、当社内で利用しているSalesforceをはじめとする各種ツールとの連携性です。当社は契約管理にクラウドサインを使用していますが、そことも連携できるのはいいですね。最後に直感的な操作性です。特定の人しか使えないツールは属人化します。帳票DXの操作性であれば、少しシステムが分かる人間であればメンテナンス可能だろうと思いました。」(梁田氏)
【運用・評価】煩雑な処理を解消し対応工数を1/2に削減 属人化しないシステムのベースができた。
続いて、実際に導入された後の運用状況やその効果について伺った。
「Salesforceと帳票DXの導入により、ダブル入力やデータ照合などの工数は削減されました。それに伴う入力ミスなどのヒューマンエラーも解消されています。また、全員で活用するということも実現され、属人化しない環境を構築できたと思います。」(梁田氏)
実際オペレーション業務で使われている小林氏からは「すごく楽になった」というお言葉をいただいた。
「請求書を除く帳票、見積書・発注書・納品書などですね。そのあたりはすべて帳票DXを使っています。出力した帳票は指定のGoogleドライブに自動保存されますし、電子帳簿保存法に沿った命名規則にファイル名が自動で設定されます。1案件に10分かかっていた作業工数が半分になりました。現在動いている案件数としては月に130件ほどあるので、大きな工数削減になっています。」(小林氏)
【今後】次のステージは海外 ますます拡がる事業を支える機能強化にも期待
最後に今後の展望やオプロ、その他製品への期待について伺ったところ、現在進行中の取り組みについて伺うことができた。
「帳票DXについては現在Maar事業部が先行して使っていますが、LIMEX事業本部でも徐々にリリースしていく予定です。あとは、まだ一部先方都合などで紙でのやり取りが残ってはいるのですが、ゆくゆくはすべて電子化したいですね。」(梁田氏)
「Maar事業部については、今年度中に海外対応が必要となることが決定しています。通関書類などやはり国内対応の書類にはない項目もあるので、きちんと準備・対応していければと思います。」(小林氏)

地球の未来を担う事業を展開するTBM。TBMの方たちの名刺には、自分で決められる肩書が入っている。小林氏の肩書は、「夢八訓」の冒頭にある「夢ある者」。着実に目標に向かう同社の姿勢さながらだと感じた。その目標に向かうためのあらゆる取り組みの中に、オプロの製品を選定いただいたことを光栄に感じるとともに、同社の事業拡大をきちんと支えられるようさらに精進していきたいと思う。
※記載されている内容は、取材当時のものです。(取材日:2025年1月30日)